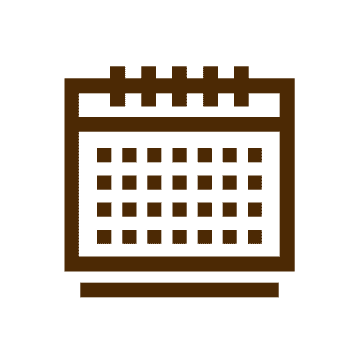2023/07/28
合宿免許や運転免許、教習に関する用語を詳しく解説!
50音順に並んでいるので目的の用語も探しやすい!合宿免許を調べていて、学科の勉強をしていて気になる言葉に見つけたらぜひ活用下さい!
「あ~お」で始まる用語
あで始まる用語
| IC免許証 |
ICチップを埋め込んだ運転免許証のこと。 埋め込まれたICチップには、古い運転免許証(2010年6月以前に発行された免許証)で本籍欄に書かれていた個人情報が記録されている。 古い運転免許証と比べた時のメリットに、偽造・変造しにくいことやプライバシーがわかりにくいこと等があげられる。 |
|---|---|
| 合図 |
交通における「合図」とは、車の運転者が右左折、進路変更、転回、徐行、停止、後退等を行う時に、手やウィンカーを適切に使って周囲の通行者にその行為を知らせることである。 合図はあらかじめ安全を確かめてから行い、行為が終わるまで継続しなければならない。 |
| アイドリング |
車が止まっている時に、アクセルを踏まない状態でエンジンが低回転していること。 これを行わないことにより排気ガスを抑えられる為、地球温暖化防止につながる。 |
| 隘路 |
中型・大型(一種・二種共通)の第一段階で行われる課題の一つ。狭くて通行の困難な道を通る。 課題内容は右折か左折で走行線からはみ出すことなく進入し、止まる事なく90度車体の方向を変え、進入範囲(2本のラインの間)に車体を収めるものである。 |
| アウトバーン |
ドイツで幹線道路の役割を果たしている、自動車専用の高速道路。 特定の場所や車種を除いて速度制限がない。 |
| 青切符 |
交通反則切符のこと。交通違反の中で、行政処分点1〜3点の軽微な違反に発行される。対象車両は、原動機付自転車・自動二輪車・自動車である。 青い紙に書式が印刷されているので「青切符」と呼ばれている。 類似したものに赤切符があるが、前科が付くか付かないかの違いがある。 |
| 赤切符 |
交通切符(告知書)のことである。交通違反の中で、交通反則切符の適用を受けない行政処分点6点以上の重度な違反・人身事故の際に発行される。 赤い紙に書式が印刷されているので「赤切符」と呼ばれている。 |
| アクセル | エンジン回転数を操作する為の装置、特にペダルのこと。 |
| アフターファイヤー |
エンジン内で燃焼しきれなかった燃料(未燃焼ガス)が、排気管の中でエキマニやマフラーの熱によって引火し爆発・燃焼して、マフラーから音や炎が出る現象。 エンジンブレーキの減速時やギヤチェンジに発生するケースが多く、燃料噴射量の調整が不十分であったり点火時期が遅れたりすることなどが原因の大半である。 アフターバーンと呼ばれることもある。 |
| アームレスト |
座っている人の腕が疲れないように、座席の側に設けられる肘掛け。 自動車の場合は、座席と座席の間につけられることが多い。 |
| RPM | エンジンの回転に関する単位。「Revolution Per Minute(回毎分)」の略語であり、文字通り1分ごとにエンジンがどれだけ回転したかを表す。 |
| RV |
レジャー用の自動車(recreational vehicle)のこと。オフロード走行ができるなど、アウトドアレジャーに使われるのに適した機能を持つ。 類似したものにSUV(sports utility vehicle)がある。 |
| アルミホイール | アルミ合金製の車輪のこと。デザイン性がよい、軽量である等のメリットがある。 |
| 安全運転管理者 |
一定台数以上の自動車を使う事業所等において、自動車の安全運転に必要な業務を行う者。定員11人以上の自動車が1台以上、またはそれ以外の自動車が5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)ある事業所で1名設ける必要がある。 登録する際は、一定の資格を持った人を事業所の中から選任し、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会に届け出る必要がある。 |
| 安全確認 | 運転中は、安全のため、安全確認として前方だけでなく後方や側方の状況もつかみ、進路変更等するときには他の交通に迷惑をかけないようにしなくてはならない。 |
| 安全地帯 |
道路標識などにより安全な場所として示された、路上の部分。路面電車の利用者や道路の横断者など、歩行者の安全を図るために設けられている。 車両は進入禁止であるほか、そばを通るときも、この地帯の中に歩行者がいる場合は徐行しなくてはならない。 |
| アンダーステア |
自動車の操縦上の性質の一つ。自動車のハンドルを切っているとき、車の速度を上げると、車体の向きがあまり変わらず回転半径が大きくなる(カーブする場合は、カーブの外側に膨らんでいく)。 一般の乗用車は、安全性のため弱いアンダーステアに設定されている。 |
| アンチロックブレーキシステム(ABS) |
自動車が急ブレーキをかけたとき、車輪の回転が停止(ロック)することを防ぎ、安全に止まるようにした装置。 ロックを防ぐことで、ハンドルの操作やタイヤと地面との摩擦が効くようになる。 |
いで始まる用語
| 行き違い | 対向車と行き違うときは安全な間隔を保たなければならない。 |
|---|---|
| 一時帰宅 |
合宿免許において、合宿期間中に一旦帰宅して、合宿に復帰すること。 一時帰宅が認められていない学校や、条件付きで認めている学校も少なくないため要注意。 |
| 一時停止 |
標識や赤の点滅信号などの前で、走行中の自動車などがいったん止まること。 停止する位置は、停止線の直前(線がない場合は交差点の直前)である。 止まった車は、交差する道路を通行する車などの進行を妨げてはならない。 |
| 一時停止違反 |
一時停止を行わなかった時に問われる違反。 反則点数は2点・罰金は7千円である。 |
| 一方通行 |
車両の通行が一方向(道路標識の矢印の方向一つ)だけしか許可されていないこと。 主に道路の幅が狭い対面通行の困難さによる措置であるが、その一方で周辺道路との交差面で安全性を向上させたり、右折車(右側通行においては左折車)による渋滞発生を抑えるために、比較的幅員に余裕のある道路であっても、一方通行にさせる場合がある。 一方通行路の出口には「車両進入禁止」の標識がついている所が多い。 |
| 違反者講習 |
免許を所持する特定の交通違反者が、免許停止処分にならないための講習。 軽微(3点以下)な違反行為をして累積点数が6点になった人が対象となる。過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった人は受講できない。 対象となった人には、公安委員会から通知が来る。講習を受けられる期間は、通知を受け取った翌日から30日までである。 |
| ETC | 有料道路の料金所で止まらずに通行料を精算できるシステム。「Electronic Toll Collection(電子料金徴収システム)」の名前の通り、無線通信やICカードといった電子式の装置を用い、通行料をクレジット式で引き落とせるようにする。 |
| インジケーター |
指示計器のこと。自動車においては、運転席の前にある計器類や警告灯などのランプをさす。 エコ運転をドライバーに促す機能を持ったものもある。 |
| インターチェンジ | 高速道路と一般道路を結ぶ施設のこと。道路法には自動車専用道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設と交差させようとする場合の当該交差の方式と定義されている。 |
| インパネシフト |
シフトレバーがステアリングホイール(ハンドル)の近くにある配置状態のこと。 ホンダ車がセンターパネル内にATのシフトレバーをレイアウトしたのが最初。 手が届きやすいハンドルの近くにシフトレバーがあるので、操作性に優れている。 |
うで始まる用語
| ウインカー | 方向指示器のこと。自動車などに付けられる保安部品で、右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示す役割がある。 |
|---|---|
| 右折 | 車や人が右に曲がって進むことである。道路が右に折れていることにもいう。 |
| 運転適性検査 | 運転適性検査とは心理検査の一つです。心理検査は性格などの個人の特徴を測定する方法で、あらゆる分野で使われている。 |
| 運転免許 |
自動車や原動機付自転車の運転を許す法的な資格。運転免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証という。 日本の制度では、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行っている。しかし、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っており、運転免許は国家公安委員会・警察庁交通局の管理監督を受ける国家資格となっている。 |
| 運転免許試験場 |
運転免許試験のみならず、運転免許にまつわる様々な手続きを行う場所。 各都道府県公安委員会の管轄下で、警視庁及び道府県警察本部が業務を行っている。そのため、各都道府県に一か所以上(主に主要都市など)設置されされている。 免許を取りたい場合、住民票のある運転免許試験場から運転免許証を発行してもらう事になる。 |
| 運転免許申請書 | 運転免許を取得する際、受験前に試験場で受け取る書類。申請手数料を渡して、該当金額の証紙を貼った状態の用紙を受け取ることがある。 |
えで始まる用語
| S字 | Sの字に曲がった形状の道路。教習所内のコースに設けられている。 |
|---|---|
| AT | オートマチックトランスミッション |
| MT | マニュアルトランスミッション |
| Nシステム |
「自動車ナンバー自動読み取り装置」のこと。 警察庁が犯罪捜査を目的に設置・運用したカメラ装置。装置は設置場所を通過する全車両の通貨時刻を自動的に撮影して記録する。 |
| エンジン |
様々なエネルギーを機械の力に変える装置のこと。一般の自動車では内燃機関の事を指す。 語源はラテン語のインゲニウム(ingenium)で、『生まれながらの才能』を意味した。 |
| エンジンブレーキ |
走行中に駆動輪がエンジンを逆に駆動して、エンジンの抵抗によって生じる制動作用である。 簡単にいうと、足で踏むブレーキではなくエンジンの回転を利用したブレーキである。ギアをダウンすることで回転が抑制され制動力が働く、これがエンジンブレーキである。あくまでも装置的なものではなく、ギアによって自然に働く制動力のことである。 |
| 遠心力 | カーブや曲がり角でカーブすると慣性による遠心力が働く。遠心力が摩擦抵抗より大きくなると、曲がり切れずに路外に飛び出したりすることもある。カーブでは常に遠心力について考えなければならない。 |
| エンスト |
使用者の意図に関わりなくエンジンが停止することである。 MT車を運転している時に多いのが、発進時のクラッチ操作やギヤの選択を誤ってエンストを起こしてしまうことである。 |
おで始まる用語
| 追い越し | 車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること。周囲の状況によっては法令で禁止されている。 |
|---|---|
| 追い抜き | 車が進路を変えずに、進行中の車の前方に出ること。止まっている車の横を通り過ぎることは「追い越し」にも「追い抜き」にもならない。 |
| 応急救護 |
指定自動車学校で行われる教習の一つ。交通事故にあった際、人命救助のため適切な行動をとれるようにするための訓練。普通一種では、学科教習の第二段階で行われる。 内容としては、事故発生直後から救急隊などの到着までの間に負傷者に対しての救命処置の方法を講習する。 特定の職業・資格がある人(医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・準看護師・救急隊員など)は受けなくても良い。 |
| 応急用タイヤ | パンク等により、装着しているタイヤが使用できなくなった時の、一時的に使用するスぺアのタイヤのこと。 |
| 横断歩道 |
歩行者が道路を安全に横断するため、道路上に示された区域。 歩行者と車両の両方から見やすいように、舗装面に白色のペイントによる縞模様が描かれたものが多い。 |
| 大型自動車 | 自動車の区分の一つで、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上のいずれかの条件に該当する四輪車をさす。区分の条件は道路交通法で規定されている。 |
| 大型自動二輪車 |
総排気量が400ccを超える二輪車(側車付きのものを含む)。 大型自動二輪車(MT)の免許を取得したら、ほぼすべての二輪車を運転できるようになる。 |
| 大型特殊自動車 |
キャタピラー付きの自動車やロードローラーなど特殊な構造をもつ、小型特殊自動車を除いた自動車。 大型特殊自動車の免許を持っているということは、このような車両で公道を走れるという事であり、フォークリフト等の付随する機械も操作できるわけではない。そのため、大型特殊車で作業をするには、他の作業免許と組み合わせて取得することになる。 |
| オートマチックトランスミッション | 自動車の変速装置の一種。アクセル・ブレーキペダルだけで速度を調節できる。そのため、クラッチやギアの操作を必要とせず、運転の難易度はMT車と比べて程度下がる。 |
| オドメーター |
走行距離計のこと。車のメーターパネルの中についている。 車が完成してから現在まで何キロ走っているか(累計走行距離)を示している。 |
| オーバーステア | 自動車の操縦上の性質の一つ。自動車のハンドルを切っているとき、車の速度を上げると、車体の向きが大きく変わり回転半径が小さくなる(カーブする場合は、カーブの内側へ回り込んでいく)。 この特性を持つ車は、速度の限界を超えると進路の制御ができなくなる。 |
| オーバーヒート | エンジンが、適正な冷却水の水温を超えて熱くなってしまい、適正に機動できなくなってしまうこと。冷却液不足など、冷却システムの不調が原因である。 |
| オービス |
アメリカのボーイング社で開発された自動式速度取締測定機の通称。 高速道路などで制限速度を大幅に超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレートおよび運転者の撮影を行う。 |
「か~こ」で始まる用語
かで始まる用語
| 外国免許切替申請 |
有効な外国の運転免許証を所持している者が、日本の運転免許に切り替える為に行う申請。 一定の資格を満たした者(書類審査あり)が、各都道府県の運転免許センターで行う。 |
|---|---|
| 外免切替 | 外国免許切替申請 |
| 学科教習 |
自動車教習で行われる、知識面の事を教える座学講習。 1段階では、交通に関する基本的なことを学ぶ(交通ルール、免許制度など)。 2段階では、応用的で実際の運転に即した事を学ぶ(けん引、高速道路での運転など)。また、安全運転ディスカッションや応急救護も学ぶ。 |
| 合宿免許 | 免許を取得するための教習の受け方の一つ。一定の期間を宿泊施設で過ごしつつ、 教習を集中して受ける。 |
| 過積載 |
重量の制限を超えて荷物を積むこと。重量制限を超えると、下記のことが発生する。 ①ブレーキのききが悪くなり、制動距離が長くなります。②振動や騒音が大きくなります。③排気ガス量が多くなる。 高さの制限を超えると、下記のことが発生する。 ①ガードや歩道橋などに衝突しやすくなる。②踏切を通過する時に架線を切断しやすくなる。③重心が高くなりカーブで横転しやすい。 |
| カースクール | 自動車学校 |
| カーナビ | カーナビゲーションシステム |
| カーナビゲーションシステム |
自動車の現在位置と進行方向を画面上に表示する装置。目的地への道案内をするのが主な機能である。道案内は音声による指示を併用することが多い。 略して「カーナビ」ともいう。 |
| カブリオ | オープンカーのこと。 布やビニールなどを使用した、折りたたみ式の屋根を持つ。 開放的な走りを楽しむ趣味的な車として使用されたり、パレードや式典で使用されたりしていることが多い。 |
| カブリオレ | カブリオ |
| 仮運転免許 |
日本の運転免許証の1つ。これから自動車運転免許を取得しようとする人が、公道上で運転の練習を行うために必要な運転免許である。一般的には「仮免許」や「仮免(仮免)」など略して呼ばれることが多い。 通学免許で仮運転免許まで取得した人が、すぐに免許が必要なため合宿免許で「仮免入校」するということもある。 種類は3種類あり、普通一種用の普通仮免、準中型車用の準中型仮免、中型一種・中型二種用の中型仮免、大型一種・大型二種用の大型仮免がある。 |
| 仮免 | 仮運転免許の略称。 |
| 過労運転 | 過労の時は注意力、判断力が衰えるので運転は控えなければならない。 |
きで始まる用語
| 規制速度 | 標識や表示によって最高速度が指定されている道路では、規制速度を超えて運転してはならない。原付に限っては時速30キロメートルを超えて運転してはならない。 |
|---|---|
| キックダウン |
走行中のAT車でアクセルペダルを大き踏み込んだとき、より低速なギアに切り替わり、急加速すること。 高速道路に入るとき等に使われる。滑りやすい路面や急カーブでこの操作を行うと危険である。 |
| 軌道敷 |
道路において、路面電車が通行する為に必要な部分。レールの内側とその両側0.61mの範囲をさす。 車は原則通行不可能である。止むをえず、または標識に従って進入する時も十分に確認する必要がある。 |
| 技能教習 | 運転の技術を教える教習。実際の車を使って行うことが多い。 1段階では、基本的な運転操作を学校コース内で練習する(S字・クランクなど)。 2段階では、路上においてより実践的な運転操作を練習する(高速教習など)。 |
| 技能修了検定 |
指定自動車教習所で、第一段階をクリアするのに必要な運転技能の検定。仮運転免許を取得して路上教習を受けられるようになるには、この検定に合格することが必要。 採点方法は減点方式となっていて、100点満点から減点されていく。試験終了時に、点数が70点以上残っていれば合格となる(大型自動車・中型自動車は60点以上)。 一般的に「修了検定」「修検」と呼ばれる。 |
| 技能卒業検定 |
指定自動車教習所を卒業するとき、最後に必ず行われる運転技能の検定。この検定に合格すると、教習所を卒業した事になる。 卒業検定では、主体的に、安全に走れるかどうか、路上での停車及び発進手順が見られる。 |
| 技能審査合格証明書 |
運転免許についている限定条件(普通免許AT限定免許・中型8t限定免許など)を教習所で解除する場合、規定の教習を終えた後で技能審査に合格すると交付される証明書。 合格した日から起算して3か月間有効である。 |
| キャブレター |
電気などの動力源を利用せずにガソリンと空気を混合する装置である。 ガソリンエンジンを搭載した自動車やオートバイでは古くからキャブレターが利用されてきたが、排出ガスの規制や性能への要求が高まるにつれて燃料噴射装置(フューエルインジェクション)が採用されるようになっている。 |
| 教習所 | 自動車教習所(自動車学校・モータースクール)のこと。運転免許を取得したい人に、自動車の運転に関する交通ルールなどの知識や、運転に関する技術を教習させる施設である。 |
| 行政処分 |
交通違反や交通事故を起こした人に対し、将来の道路交通上の危険を防止するため、運転免許を取消したり効力を一定期間停止すること。 運転免許における行政処分には、免許取消処分・免許停止処分・免許拒否処分・免許保留処分・運転禁止処分がある。 |
| 緊急自動車 | 交差点やその付近で緊急自動車が近づいてきた場合は、進路を譲らなければならない。 |
くで始まる用語
| 空走距離 | 運転者が危険を感じてからブレーキをかけ始め実際に聞き始めるまでの間の車が実際に走る距離。 |
|---|---|
| クーペ |
自動車の形の一種。2ドア・2人乗りの箱型自動車。車高が低く、スポーティな形をしている。 元々は箱型馬車の事を指す言葉であった。 |
| クラクション | 警笛 |
| クラッチ | マニュアル車に装備されている動力伝達装置。原動側(エンジン)の力を従動側(ギア・車輪)に伝える。必要に応じてエンジンとギアの間を繋げたりさえぎったりできる。 |
| クランク |
角の狭いカーブが二つ交互に繋がっている道路形状。桝形(ますがた)道路などとも呼ばれている。 教習では、教習生が苦労する項目で、深く入り過ぎたり、速度が速すぎたり、ハンドルを回し足りなかったりすると、外側前輪を乗り上げてしまい脱輪させてしまう。 |
| クリープ現象 |
AT車が、エンジンがかかっている状態でブレーキを緩めると車両がゆっくりと動く現象。 渋滞時や駐車時のスピード調整がしやすい・坂道発進の時に車両が後退しないといった利点がある。一方で、ドライバーの意思に反して車が動き出すことから、衝突事故が発生しやすいという危険もある。 |
| 車など |
交通用語で、車と路面電車のこと。 つまり、交通ルールにおいて「車など~」とあるときは車と路面電車が対象になる。 |
| グローブボックス | 自動車のダッシュボードについている小物入れのこと。かつては、運転用の手袋を入れるためのものだったのでこう呼ばれるようになった。高級車やオープンカーではリッドに鍵を備えて盗難防止に対応しているものがある。 |
| グロープラグ |
ディーゼルエンジンを暖める装置。 ディーゼルエンジンが始動し、点火するのを助ける役割を持つ。 |
けで始まる用語
| 軽車両 |
道路交通法で、原動機をもたず、レールで移動しない車両のこと。自転車やリヤカー・牛馬などがこれに当たる。 (身体障がい者用の車いすや小児用の車は歩行者として扱われる。) |
|---|---|
| 警笛 | 自動車などにおいて、自らが近づく事を音を使って他の通行対象に知らせるために使用する保安用具である。 |
| 欠格期間 |
免許の拒否・取消の処分に当たり運転免許を受ける事のできない期間のこと。 取消処分では、違反点数に応じて取消後の「欠格期間」が1年~10年定められており、この期間は運転免許の再取得ができません。 |
| 検査 | 車検ともいう。一定の時期に検査(車検)を受け、自動車検査証の交付を受けなければ運転できない。 |
| けん引自動車 |
自動車の形態の1つで、他の車をけん引するための構造や装置を備えた自動車のことである。 トラクター、キャリアカー、レッカー車などがこの種類に当たる。 けん引車を車の総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引して運転する場合は、けん引免許が必要になる。 |
| 原付 | 原動機付自転車の略称である。 |
| 原動機付自転車 | 二輪車の車両区分。道路交通法では50cc(0.6kW)以下、道路運送車両法では125cc以下(1.0kW)の原動機をもつものとする。一般的には、省略して「原付(げんつき)」をはじめ「原チャリ」「原チャ」と呼ばれる事もある。 |
| 限定解除 | 限定解除審査の略。 |
| 限定解除審査 |
限定条件のある免許を、限定条件のない免許に変更するための審査のこと。自動車学校、または各都道府県の運転免許センターで受けることができる。 AT限定免許(四輪、二輪)・普通自動二輪免許小型限定・大型特殊自動車免許カタピラ車限定又は農耕車限定・中型自動車免許8t限定・準中型自動車免許5t限定、大型車免許マイクロバス限定などがある。 |
| げん惑 | ライトを直接目に受けるとまぶしいため一瞬目が見えなくなることをいう。そのため、対向車と行き違うときは前照灯を下向きにして相手がまぶしくならないようにする必要がある。 |
こで始まる用語
| 効果測定 | 自動車の教習で、修了検定や卒業検定を受ける前に受ける学科の模擬試験。 |
|---|---|
| 交差点 |
2本以上の道路が交わる場所。 道路交通法上は、「十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分」を指す。 事故が多発する場所であるため、交差点を通過する時は、ルールを守るとともに周囲の状態をよく見ることが大切になる。 |
| 更新 |
運転免許では、免許証の有効期限を更新することをさす。 更新の際に、優良運転者講習・一般運転者講習・違反運転者講習・初回更新者講習のいずれかを受けることになる。講習の種類によって更新手続を行う場所や手数料が異なる。 |
| 高速教習 |
高速道路を走行する教習。技能教習の第二段階で行われる。 実際に高速道路を走らず、シミュレーターで代用する場合もある。 |
| 高速催眠現象 | 高速道路での運転は道路の環境等が単調であり、かつ運転操作も少ないため、意識レベルが低下し、居眠り運転が発生したりする。 |
| 交通事故 |
運転者は仮に運転中に違反を犯したり、事故を起こしたりすると下記の責任を負わねばならない。 ①刑事上の責任②行政上の責任③民事上の責任。 |
| 交通切符 | 赤切符 |
| 交通反則切符 | 青切符 |
| 公認校 |
指定自動車教習所 対:非公認校 |
| 高齢運転者標識 |
道路交通法に基づく標識の一つ。70歳以上の運転者が運転する普通自動車の、車両前後に付ける。マークの表示は努力義務(罰則なし)である。 デザインは、涙型で左半分が橙色・右半分が黄色のもの(旧デザイン)と黄緑色・緑色・橙色・黄色の四つ葉型(新デザイン)のものがある。 |
| 高齢運転者マーク | 高齢運転者標識 |
| 高齢者講習 |
満70歳以上の人が、運転免許証の更新を申請する前に受けるべき講習。有効期間満了日の6か月前から受講できる。 運転適性の指導や教習所のコース内運転指導などが行われる。さらに、75歳以上の人はこれらの講習に加えて認知機能検査も受けることになる。 |
| 小型特殊自動車 |
特殊自動車で、最高速度やサイズが一定以下のもの。 道路交通法では、農耕用か否かは関係なく時速15km以下、長さが4.7m以下、幅が1.7m以下、高さが2.8m以下の特殊車を指す。 道路運送車両法ではほとんど変わらないが、農耕用車両のみ最高速度が時速35km以上のものと定義される。 |
| 五点確認 |
二種免許の教習で教えられる、基本的な安全確認の手順。大型二種を除く全ての二種免許で欠かせない。 一般的には、ルームミラー・左ミラー・左後方目視・右ミラー・右後方目視のこと。直接目視は左右それぞれの「後方」であって「側方」ではない。 大型二種免許では、五点確認の代わりに七点確認がある。 |
| 小特 | 小型特殊自動車 |
| コーナリング | 道路やサーキットコース等のカーブを曲がること。主にモータースポーツを中心に用いられる。 |
| コーナリングアプローチ | カーブに差し掛かる方法。 |
| コーナリングテクニック | カーブを曲がる技術。 |
| コーナリングフォース | カーブを曲がる時に働く力。接地面に発生する摩擦で、遠心力に負けず、進行方向に対して直角に元に戻ろうとする力がタイヤに働く。 |
| コーナリングワーク | コーナリングテクニック |
| ゴールド免許 |
「優良運転者免許証」という別名の通り、5年以上運転免許を受けている無事故無違反者用の自動車運転免許証。平成6年から、改正道路交通法で導入された。 ゴールド免許は免許の有効期間が5年あり、他の区分(ブルー・グリーン)の免許に比べて長い。 |
| コラムシフト |
シフトレバーがハンドル軸に付いている配置状態のこと。 操作性がしやすく、足元を広く利用できる。また、前席をベンチシートとする事により前席左右の通りぬけも容易になる。 しかし、AT車では限られたレバーストロークで多くのレンジを設定できないため、ギアの段数が多くなると操作性が悪くなってしまう。 |
| コンバーチブル | 自動車では、幌やハードトップの取り外しができ、屋根付きとオープンカーの切り換えが可能な自動車のことを指す。 |
「さ~そ」で始まる用語
さで始まる用語
| 最高速度 |
最高速度とは、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度のことである。 各種交通機関などに対して法令で定められており、制限速度とも規制速度とも言う。最高速度は、規制速度算出要領によって決められていたが現在は廃止され、各県が自由に設定できるようになった。しかし、実際にはこの規制速度算出要領に基づき最高速度を決めている自治体が多い。 |
|---|---|
| サイドブレーキ | サイドブレーキとは、手動式の制動機構のことであり、駐車ブレーキやハンドブレーキとも呼ばれている。駐車時のみならず、フットブレーキの故障などで車を停止できなくなったときの非常用ブレーキとしても制動手段として使用される。 |
| 左折 | 左に折れ曲がること。 |
| サービスエリア(SA) |
サービスエリア(SA)とは、高速道路等に概ね50kmおき(北海道は概ね80kmおき)に設置される休憩施設のことである。高速自動車国道法により、高速道路内の路肩には商業施設などを建てることができないため、休憩・食事・自動車の給油・整備点検のための施設として設置される。 一般に駐車場・トイレ・無料休憩所・緑地・遊具施設のほか、レストラン・売店・情報コーナー・給油・修理所(ガソリンスタンド)などが設けられるのが普通である。2000年代頃から、マクドナルドやスターバックスといったチェーン店を導入したり、売店の代わりにコンビニエンスストアを導入するSAが増加している。 |
| サーモスタット |
サーモスタットとは、一言でいうと「温度調節機」である。 冷却水の循環経路の途中に設けられ、水温が低いときは閉じて、水温が高くなると開いて冷却水をラジエーターに循環させてエンジンの温度調節を行う装置。これが故障するとオーバーヒートしたり、逆にヒーターが効かなくなったりする。 |
| サルーン | サルーンとは、セダンの別称で英国での呼び名。別の呼び名としてドイツではリムジーネ、フランスではベルリーヌ、イタリアではベルリーナ と呼ばれる。米国や日本ではセダンが一般名称となっているが、上級グレードの商標としてサルーンが用いられることが多い。 |
| 残存歩行者 | 青信号中に渡りきれない人。 |
しで始まる用語
| 時間制限駐車区間 | 同じ車両制限した時間の間で継続して駐車をすることができる道路の区間。この区間では道路標識により利用できる時間帯と駐車時間が指定されている。 |
|---|---|
| 失効 | 運転免許証に記載されている有効期間内に運転免許の更新手続きを行わなかった場合、有効期間の満了で運転免許は失効となる。もし運転免許が失効まま運転したら無免許運転となる。 |
| 指定自動車教習所 |
道路交通法第九十九条に基づいて都道府県公安委員会が指定した自動車教習所(自動車学校)のこと。 指定自動車教習所で所定の課程を修了した者に対しては、道路交通法の規定により、技能試験が免除される。ただし1年以内に学科試験や適性試験に合格しないと無効となる。 |
| 指定方向外進行禁止 | 道路標識により、矢印が示す方向以外への車両の進入を禁止すること。車両の進行を禁止する交差点の手前や中央分離帯、当該交差点に係る信号機付近に道路標識が設置されている。 |
| 自動式速度取締測定機 | オービス |
| 自動式ナンバー読取照会システム | Nシステム |
| 自転車 | 乗り手自身の人力を主たる動力源として、車輪を駆動する事で推進力を得、地上を、乗り手の運転操作に応じて自在に進路を選んで走行する乗り物である。 |
| 自転車横断帯 | 標識や表示により、歩行者が横断するための場所であることが示されている道路のこと。 |
| 自転車道 | 自転車の通行のため様々な工作物により区分された車道の部分。 |
| 自動車学院 | 自動車学校のこと。「自動車教習所」「ドライビングスクール」などと呼ばれることもある。 |
| 自動車学校 |
自動車を運転するために必要な知識と技能の教習を行う施設。 運転免許を取得しようとする者は自動車学校で知識や技能を習得する。自動車学校の呼び名の他に「自動車教習所」「自動車学院」「ドライビングスクール」などと呼ばれることもある。 |
| 自動車教習所 | 自動車学校のこと。「自動車学院」「ドライビングスクール」などと呼ばれることもある。 |
| シートアジャスター | 自動車の座席を乗員が好む姿勢に調整する装置。 |
| シートベルト | ベルト状の安全装置で、安全ベルトとも呼ばれる。座席に乗員の身体を固定させることで座席の外へ投げ出されて負傷することを防ぐために使われる。自動車のほかに、飛行機やロケットなどの乗物にも取り付けられている。 |
| シートリフター | 自動車のシートを乗員が好む高さに調整できる装置。 |
| GPS | Global Positioning System(全地球測位システム)の略で、米国によって運用される衛星測位システム(地球上の現在位置を測定するためのシステムの事)を指す。 |
| 車間距離 | 走行する車と車の間の距離のこと。前方の車が急に止まっても、追突しないような距離をとらねばならない。 |
| シャシー | 自動車の車体(ボディー)を除いた骨格となるフレームのこと。シャーシ、シャシ、シャーシーとも呼ばれる。 |
| 車線 | 安全かつ円滑に車両の通行を行えるように設置された帯状の線。車線の種類には走行車線のほか、追越車線や登坂車線、屈折車線、変速車線などがある。 |
| 車道 | 車両や路面電車が通行するために定められた道路の部分。 |
| 車両横断禁止 | 標識や標示によって車両の横断が禁止されること。交通量の多い幹線道路などに設けられている場合が多い。 |
| 車両進入禁止 | 標識や標示によって車両が一定の方向に進入することを禁止されること。逆方向から来る車両との鉢合わせを防ぐため、一方通行の道路に設置されている場合が多い。 |
| 車両通行帯 | 道路の定められた部分を車両が通行するために、白線などの道路標示によって示されている道路標示。片側2車線以上ある道路では、同じ方向に走る車との間に示される。 |
| 修検 | 技能修了検定 |
| 修了検定 | 技能修了検定 |
| 重量制限 | 車両の総重量が標識などに示された重量を超える場合は通行を制限される。総重量とは車両と人、積載荷物を合計した重となる。 |
| シュミレーター | 自動車教習所で教習生が自動車の運転を学ぶために使用する擬運転装置。実車では危険が伴う可能性の高い高速道路や雪道といった場面での練習を行うためにも使用される。 |
| 順応 | 暗いところから急に明るいところへ出ると、最初はまぶしくてよく見えないが目が慣れ、通常道理に見えるようになる。これを明順応。逆に明るいところから暗いところへ行ったときも初めはなにも見えないが次第に見えるようになる。これを暗順応。暗順応のほうが明順応よりも時間がかかる。 |
| 消音器 | エンジンの排気音や吸気音を低減する装置。マフラーとも呼ばれる。この装置の形状によって、エンジンの出力が左右される。 |
| 蒸発現象 | 自分の車のライトと対向車のライトで道路中心付近の歩行者や自転車が見えなくなること。 |
| 徐行 | 徐行とは、道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。具体的な速度は示されていないが、ブレーキを操作してから停止するまでの距離が概ね1m以内の速度なので時速10km以下の速度であるといわれている。 |
| 初心運転者標識 |
初心運転者標識とは、日本の道路交通法に基づく標識の1つである。矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事から一般的には若葉マーク・初心者マークと呼ばれている。 普通車免許の取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務がある。取得後1年以上の者が初心者マークを表示した車を運転しても、規定がないので法律上の問題はない。 |
| 初心者マーク |
初心者マークとは、初心運転者標識の別称である。 普通車免許の取得後1年を経過しない運転者は、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4 – 1.2m以内)に掲示する義務がある。 |
| ジレンマゾーン |
ジレンマゾーンとは、信号機が黄色に変わったときに、交差点の手前で進むべきか停止すべきか悩む範囲のことである。 ここで注意が必要なのは、黄色は注意進行ではなく基本的には「止まれ」であることです。あくまでも安全に止まれない時だけ進むことができる。 |
| 信号・信号機 | 信号・信号機とは、鉄道や道路における交通の安全の確保・交通の流れを円滑にするために、進行・停止などの信号を示す装置である。道路上において交通整理を行う色は世界共通で、緑・黄色・赤の3色である。対面する信号機の緑は「進んでもよい」(通行許可)、黄色は「停止線で止まれ。急停車となる時はそのまま進むことができる」(停止)、赤は「進んではいけない」(進行不可)である。 |
すで始まる用語
| スキッド教習 |
自動車学校で行われる、危険を体験するための教習の一つ。 冬場に凍ったり雪が積もったりした道路を疑似的に体験させ、スリップしやすい道路の走り具合や危険性についてを教える。 冬場の道路を再現する方法には、車両に特殊な機器をつけたり、専用の教習コースを作ったりするなどのことがある。 |
|---|---|
| スクーター | 二輪車の一種。足置き台が前方にあり、またがらないタイプになっている。 |
| スクールゾーン | 小学校や幼稚園を中心とした、半径約500メートル程度の、通学路に指定された範囲。一定の時間内に車両の通行が制限される。 |
| スタンディングウェーブ現象 |
タイヤが空気圧不足(荷物を積みすぎて車両が重くなる場合もこの状態にあたる)のまま高速走行することが原因である。 自動車が走っているとき、タイヤの波状のたわみが発生する現象。この状態で走行を続けると、タイヤが破裂してしまう。 |
| ステアリング | 自動車では、方向転換装置や、装置の中でも重要な部分であるハンドルのことを指す。 |
| スピードリミッター |
文字通り、自動車の最高速度を抑える装置。 道路運送車両法では、車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の大型トラックに装着が義務づけられている(時速90kmを超えることができないようにする)。 |
| スピンターン | 方向を真後ろに転換するために、意図的にタイヤを横滑りさせる運転テクニック。サイドターンとも呼ばれる。 |
| スポーク | 車輪を構成する部材の1つ。車軸の通るハブから放射状に伸びていて、車輪の外周部分を支えているリムとつながっている。 |
| スリップサイン |
タイヤが磨り減りタイヤの溝が1.6ミリ以下になると、そのタイヤの寿命がきたことを警告するサインのことである。 このサインの表れた自動車は整備不良車として扱われるため、走行することは禁止されている。 |
| スロットル |
ガソリンエンジンで、空気取得口とインテークマニホールドの間に位置し、空気あるいは混合気のエンジン内部への流入量を調整する弁のこと。 エンジンの回転数や負荷を調節する役割を持つ。 |
せで始まる用語
| 制動距離 | ブレーキが利き始めてから実際に停止するまでの間のに車が走る距離。 |
|---|---|
| セダン | 一般的には前後に2つの座席がある3ボックス型の乗用車のこと。セダンの語源は、「腰掛ける」という意味をもつラテン語のsedeo, sedoとされている。 |
| セルモーター |
自動車のエンジンを始動するための、電池式モーターのことである。 セルモーターが内燃機関の初期的な回転を発生させることで、内燃機関が燃焼による自力での回転を開始する。 |
| 前照灯 |
自動車などの前方部分につけられる照明装置。ヘッドランプやヘッドライトとも呼ばれる。 自動車では、100mほど遠くまで照らせる「走行用前照灯(ハイビーム)」と対向車が来たときに使う「すれ違い前照灯(ロービーム)」を切り替えることができる。 |
| 専用通行帯 | 標識や表示によって示された車だけが通行できる車両通行帯のこと。 |
そで始まる用語
| 走行距離計 | オドメーター |
|---|---|
| 総排気量 |
エンジンの大きさを表す単位。この数値が大きいと、エンジンも大きいことになる。 シリンダー内でピストンが1往復する時にシリンダーから排出されるガスの容積で求められる。単位はccまたはL。 |
| 側道 | 高速道路など、出入りを制限された道路に沿って設けられる道路。道路の出入り制限によって通行に支障をきたす部分のカバーが目的で設置される。 |
| 側方間隔 |
側方間隔とは、路上を通るとき、車体と側方にあるものとの間に保つべき間隔のこと。 この間隔を保つことは義務であり、自動車教習の検定でも反映される。検定では、動くと考えられるもの(人の乗った車両)とは1m以上、動かないものとは0.5m以上の間隔を空けないと減点となる。 |
| 側方通過 | 交通用語で、行き違いのこと。 |
| 卒業検定 | 技能卒業検定 |
| 卒業証明書 |
指定自動車教習所を卒業をしたことを意味する証明書。指定自動車教習所の卒業検定に合格することで発行される。 運転免許試験場で運転免許試験を受けるときにこの証明書を提出すれば、技能試験が免除される。 証明書の有効期限は、卒業検定の合格日より1年間である。 |
| 卒検 | 技能卒業検定 |
「た~と」で始まる用語
たで始まる用語
| 第一種運転免許 |
道路交通法上の免許区分。 自動車や原動機付自転車を代行運転や旅客運送などを除く目的で運転する場合(バス・タクシーの回送は可能になる)に必要な免許。 大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付などの種類がある。 |
|---|---|
| 大特 | 大型特殊自動車 |
| 第二種運転免許 | 道路交通法上の免許区分。代行運転(酒気を帯びた客などの代わりに運転する)や旅客運送(バス・タクシーなど)の目的で運転する場合に必要な免許。大型・中型・普通等の種類がある。 |
| ダイバーシティアンテナ |
2本以上のアンテナを使って複数の電波を受信し、もっとも強い電波を受信したアンテナに切り替えるアンテナ。この仕組みによって、電波の受信状況を良い状態で安定させることができる。 自動車など移動する物体に取りつけるためのものも存在する。 |
| タイヤ |
自動車などの車輪の外側を覆うゴム製の輪のこと。 車体の荷重を支える、アクセルやブレーキの力を地面に伝える、ハンドルによる方向転換の力を伝える、路面からの衝撃を和らげるという機能を持つ。 |
| タコメーター |
エンジンの回転速度を表す計器(回転計)。 エンジン回転数は、エンジンの出力を極限まで引き出したり燃料消費を抑えたりするために重要な情報である。効率よく運転するには、この計器がヒントになる。 |
| ダンプカー | ダンプトラック |
| ダンプトラック |
荷台を傾けて積荷を一度に下ろすための構造のトラック。土砂などの運搬に使われる。 荷物を下ろす方向によって、リヤ(後ろ)、サイド(横側)、ボトム(下方底)などの種類がある。 ダンプ (dump) とは、「(荷物などを)どさっと下ろす」という意味の英語。 |
ちで始まる用語
| チャイルドシート |
6歳未満の子供を自動車に乗せるときに使われる装置。 シートの上に装着して固定し、その上に子供を座らせることで、急ブレーキや事故にあった際の被害を軽減できる。 2000年4月から道路交通法で着用が義務付けられている。また、シートのサイズは子供の体格によって適切なものを使わなければならない。 |
|---|---|
| チャイルドロック | 自動車の後部アにあるレバーを動かすことで、内側から開けなくする装置。子供のいたずらなどでドアが不用意に開けられるのを防ぐ。 |
| 中央線 |
道路にある、対向車線との境界線。 必ずしも道路の中央にあるとは限らず、車線の数が片側と反対側で違うものや、交通状況(時間)によって位置が変わるものがある。 |
| 駐車 |
駐車とは、車の継続的な停止(運転席に運転手がいる場合も含む)のことである。 特に、運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることは「放置駐車」という。 |
| 駐車違反 |
駐車禁止の場所・時間帯に駐車を行うこと。 駐車禁止の道路標識・道路標示により駐車が禁止されている場所や火災報知機から1m以内の部分など、道路交通法 第四十五条および第四十六条において定められている。 |
| 駐車余地 |
駐車する時に確保が義務付けられている、道幅の余地。原則、車両の右側の道路または車道上に3.5m以上とされる。 なお、荷物の積みおろしを行なう場合で運転者がその車両を離れない場合、もしくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に戻れる場合、又は傷病者の救護のためやむを得ない場合は取らなくても良い。 |
| 駐停車禁止 | 駐車も停車もしてはならないこと。対象となる場所は、「駐停車禁止」の標識、標示のあるところ・軌道敷内・トンネル(車両通行帯があってもなくても禁止)・坂の頂上付近や勾配の急な坂(上りも下りも禁止)・軌道敷内である。 |
| チルトステアリング | ハンドル軸の傾きを上下に調節できる仕組み。ロックを外すとハンドルが移動でき、好みの位置でロックをかければハンドルの角度が調節できる。自分に合ったドライビングポジションが取れるのはもちろん、身長など体形の異なる人が運転することになっても合わせられるので非常に便利である。ほとんどの車種に装備されている。 |
つで始まる用語
| 通学免許 |
自宅に近い教習所に通いながら、運転免許取得を目指す方法。 自分のペースで教習を受けられる、見慣れた場所で路上教習ができるなどのメリットがある。 |
|---|---|
| 通行止め | 道路が通行できなくなること。もともと標識で歩行者や特定の車の通行が禁止されている場合のほか、事故や気象条件・工事などのため、道路管理者や警察の判断により通行禁止になることもある。 |
| ツーリング |
バイクで遠出をすること。 ただバイクで移動するだけでなく、バイクで走ることを楽しむため、山岳地や海岸沿いなどの走行ルートが選ばれることもこのように呼ばれる。 |
てで始まる用語
| 停止処分者講習 | 交通違反などにより、停止処分を受けた場合停止処分者講習を受けることで、一定基準により停止期間が短縮される。 |
|---|---|
| 停止線 |
交差点の入口などにおいて、車両の停止位置を示すもの。 標示の形式で地面に引かれているものと、停止線の標識を設けたもの(道路条件によって地面に線が設けられない時に使われる)とがある。 |
| 停車 |
駐車にあたらない短時間の車の停止のこと。 人の乗り降り・荷物の積み下ろし(5分以内)・運転者がすぐに運転できる状態での停止がこれにあたる。 |
| 停車違反 | 停車禁止の場所や時間帯に停車を行って違反に問われること。 |
| ディーゼリング | ラン・オン |
| ディーゼルエンジン |
エンジンの一種。高温(500~700°C)・高圧(圧縮比15~20)の空気に燃料を吹き付け自然発火させて動力を得る。 熱効率が良いというメリットがある。主にバスなどの大型車両に用いられる。 |
| 適性検査 |
特定の活動にどこまで適した性質があるかを調べる検査。 運転免許でいう適性検査には、「視力」「聴力」「色彩識別能力」「運動能力」などがある。それぞれの項目において、運転に関する状況・動作の速さ・正確さなどを自覚するための検査で、この基準値は免許の種類によって異なる。 学科試験・技能試験に合格しても、この適性検査の基準に達しなかった場合運転免許証は交付(更新)されない。 |
| 手信号 | 警察官や交通巡視員が手で行う信号。信号機の信号と警察官などの手信号が異なる場合は、手信号の方に従う。 |
| デリニエーター |
視線誘導施設の別称である。道路の側方や中央などに沿って路端や道路線形などを示すために設置される施設の総称である。昼夜間における車両運転者の視線誘導を行うことが目的である。 高速道路では50メートル間隔に設置されており車間距離の確認に使われたり、積雪地帯では除雪作業の目印として役割を果たすものがあったり、ガードレールにシート状のものを貼り付けた簡易的な形式のものもある。 |
| 転回 |
道路交通法でUターンのことを指す言葉。 進路を180度変えて、今までの進行方向とは正反対に進むことをいう。 |
とで始まる用語
| 道交法 | 道路交通法 |
|---|---|
| 動体視力 | 動きながらものを見ること、または、動いているものを見ることである。動体視力は静止視力に比べて低くなります。速度が速くなると視力が低下し、危険な状況の発見が遅れることになる。 |
| 登坂車線 | 車道の上り坂で、走行車線の外側にある車線。大型車など、坂を登るとき速度が著しく低下する車両が低速度で登れるようにする目的で設けられる。 |
| 道路 |
人や車などの通行する道のこと。 道路法では、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道のことをさす。同法律では、トンネルや橋など、道路と一体となって通行に用いられる施設も含まれる。 |
| 道路交通法 | 道路交通を安全・円滑にするため、1960年に制定された法律。歩行者や車の通行方法、運転免許や罰則の制度について定めている。 |
| 道路標識 | 道路交通を安全・円滑にするために立ててある標識。案内・警戒・規制・指示などの事項が記してある。 |
| 特定届出自動車教習所 |
届出自動車教習所(指定自動車教習所ではない) 人的基準・物的基準・運営的基準に適合するものに対し公安委員会より指定を受けた自動車教習所。 取得時講習(普通免許・二輪免許・二種免許の教習で義務づけされた、応急救護処置・高速教習・危険予測等の講習)の代わりに特定教習を行う。 全ての試験を運転免許センターで行う点が、指定自動車教習所との明らかな違いである。 |
| 飛び込み |
「一発受験」という別名の通り、指定自動車学校で教習を受けず、試験場・免許センターで実施される技能試験などを直接受験すること。 指定自動車学校で教習を受けた場合に比べて合格率が低い。 |
| ドライビングスクール | 自動車学校 |
| 取消処分 |
運転免許の効力を将来に向かって失わせる処分。 交通違反や交通事故を実際に起こしたとき、または自動車等を運転する事で道路交通にとって大変な危険を起こすと考えられる場合に行われる。 |
| 取消処分者講習 |
運転免許の取消・拒否処分等を受けた者が、再び運転免許を取得する際に必ず受講しなければならない2日間13時間の講習のことである。 講習は少人数制・完全予約制なので、早めの予約が必要である(予約は運転免許試験場または運転免許センターにて受付)。 |
| 取消処分者講習終了証書 | 運転免許の取消・拒否処分等を受けた者が取消処分者講習を受講すると交付される証書。1年間有効である。欠格期間中でも、この証書を持っていれば入校できる教習所もある。 |
| トリップメーター | 自動車の走行距離計の中でも、任意にゼロへリセットできるもの。 |
| トルク |
力学において、ある固定された回転軸を中心にはたらく、回転軸のまわりの力の量のこと。 自動車では、エンジンの回転力・駆動力のことをさす。 |
| ドロップヘッドクーペ | クーペの一種。幌を持つオープンモデルで、幌が一重ではなく完全な内張りを持っており、屋根を閉じればほぼクーペと同じ乗車空間になる。 |
「な~の」で始まる用語
なで始まる用語
| 内輪差 |
自動車が右左折する時に生じる、前輪と後輪との通行位置の差。 トラックなどのように車体が長くなると、内輪差も大きくなる。 この差に気をつけないと、道路のふちに乗り上げるなどの事故が起きる。 |
|---|---|
| 七点確認 |
大型二種の発進時の安全確認の流れのこと。普通二種などで行う五点確認「ルームミラー・左ミラー・左後方目視・右ミラー・右後方目視」に、「車内目視・車両の直前直下」の2つを追加したもの。 特に順番は決まっていないので、教習で自分のやりやすい順を身につけると良い。 |
| ナンバー |
自動車のナンバーは、国や地方政府が発行し車両の登録番号のこと。 識別のために「漢字」「かな」「数字」などによる符号が使用されている。 |
にで始まる用語
| 二種免許 | 第二種運転免許 |
|---|---|
| 入校不可地域 |
合宿免許を行う教習所がおのおの設定する、合宿で入校できない地域。 この地域内に居住地・住民票・実家・本籍があると入校できない。ただ、地域内に居住地・住民票・実家・本籍のどの条件があてはまると入校不可になるかは学校で異なる。 |
| ニーグリップ |
スクーター以外のオートバイの基本乗車姿勢の1つ。ひざを中心とした内股で燃料タンクを挟む。 このことで下半身を固定すると、上体が過度に緊張せず、ハンドル操作や体重移動を円滑に行うことができる。 ひざから下の脚全体を車体に寄せ、足はつま先の方向を車体と平行に保ち、かかとを車体に押し付けると、内股の緊張も少なく安定する。 |
| 二段階右折 |
道路の交差点で右に曲がるとき、交差点の内側ではなく輪郭に沿って曲がること。一段階目で交差点を直進し、右に向きを変え、二段階目で直進する。 交通整理の有無を問わず、自転車を含む軽車両が交差点で右折する際には、全ての交差点で二段階右折を行わなければならない。 |
| ニュートラル |
自動車では、エンジンの力がタイヤに伝わっていない状態のこと。 AT車では、長い間停止させるときフットブレーキ・ハンドブレーキと併用する場合や、けん引される場合にしか使われない。逆に、走行・発進時にこの状態にすると危険である。 |
ぬで始まる用語
| 抜け |
マフラーの排気効率のこと。 マフラー内のパイプの曲げ方が急だと抜けが悪くなり、逆に曲げがゆるやかだと良くなる。 抜けが良くなることで、車のパワーが上がる場合が多い。 |
|---|
ねで始まる用語
| 熱線 |
ガラスのくもりを防ぐため、ガラスに取り付けられた細い金属線。金属線に電気を通して加熱する。 視界を遮らないよう、細さや間隔には一定の規格がある。 |
|---|---|
| 燃費 |
エンジンが、ある一定の仕事(一定の距離を走るなど)をするとき、どのくらいの量の燃料を消費するのかを数値で表したもの。燃料消費率ともいう。 使用する燃料、タイヤ空気圧、路面状況、エンジンオイルの種類、積載重量、走行パターンなどで変化する。 ある一定の回転数で全負荷の状態で、1時間に1馬力あたりに使用する燃料消費量をグラムで表したもので、g/PShという単位を使う。一般的に、燃料消費率が小さい=燃費の良いエンジンといえる。 |
| 燃料消費率 | 燃費 |
ので始まる用語
| ノッキング |
エンジンに打撃的な音や振動が生じる現象のこと。ノックとも呼ばれる。 ノッキングには、MT車でエンジンの回転数が極端に低い状態で走行したときなどに、車体がガタガタと振動する現象「カーノック」と、ピストンエンジンがキンキン・カリカリなどと金属性の音や振動を発する「エンジンノック」の2種類が存在する。 |
|---|---|
| ノック | ノックとは、ノッキングと同意義である。エンジンが金属性の打撃音及び打撃的な振動を生じる現象全般を指す。 |
「は~ほ」で始まる用語
はで始まる用語
| ハイオク | ハイオクタン価ガソリンの略。 |
|---|---|
| ハイオクタン価ガソリン |
高オクタン価ガソリン。 レギュラーガソリンより高いオクタン価(石油燃料を内燃機関で燃やしたときにノッキングと呼ばれる障害の起こしにくさ(アンチノッキング性)の度合いが高いこと)を持つガソリン。 |
| 排気ブレーキ |
別名エキゾーストブレーキと呼ばれ、補助ブレーキの事である。 3.5t以上の大型自動車や内燃機関で動く鉄道車両が装備している。排気管路をバルブによって閉鎖し排気圧を上げることによって回転を妨げる仕組みである。 |
| バイク | 日本国内では、バイクはエンジン付き二輪車を指すことが多い。 |
| ハイビーム | 正式名称では走行用前照灯という。夜間走行する際に使用する。ハイビームとロービームの切り替えが大切である。 |
| ハイドロプレーニング現象 | 水たまりの上などを車が走った際に、滑ってハンドルやブレーキが利かなくなる現象のこと。 |
| ハイブリッドカー |
異なる2つ以上の動力源を持つ車両。 日本では狭義にハイブリッド電気自動車の意味で使用される。 複合型自動車ともいう。 |
| 倍力装置 | ブレーキブースターのこと。自動車のブレーキを構成する部品の一つで、運転手のブレーキ操作力を低減する為の補助を行うシステムである。 |
| パーキングエリア(PA) |
ドライバーが疲れをとるためにサービスを提供している施設である。 売店やガソリンスタンドは必ずしもあるとは限らない。およそ15km間隔に一つつけられる(ただし、必ずしもこの距離とは限らない)。 |
| パーキングブレーキ |
サイドブレーキ。 自動車のブレーキ機構のひとつで主に駐車時に使うブレーキ。 一般に後輪をロック(固定)させる働きを持つ。 |
| バケットシート | バケツ形の座席という意味。左右のヘリを高め、肩腰足など体を支えるのに必要な部分を深く包み込んで体の固定機能を高めた形状のシート。 |
| ハザードランプ |
非常点滅表示灯。 方向指示器(ウインカー)を同時に点灯させること。 夜間、幅員が5.5m以上の道路に駐停車するときは、非常点滅表示灯または尾灯をつけなければならない(道路交通法)。 |
| 波状路 | 自動車教習所などで自動二輪車教習や技能検定に使用される不等間隔に開いた路地のこと。 |
| バースト |
タイヤが破裂すること。 トレッド部やサイドウォール部が一気に破壊され、タイヤの機能が失われるため、深刻な事故を招くことが多い。 |
| 発炎筒 | 自動車等に装備される、鮮やかな赤い炎を上げる筒状の道具。緊急の際に使用され、後続車に対し前方に危険・障害物がある事を知らせるために用いられる。 |
| バックファイア | 内燃機関でエンジン内部から気化器や吸気管に炎が逆流する現象である。ただちに、修理が必要である。 |
| 幅寄せ | 自動車などの運転における行為のこと。2つの異なる意味が存在する。①駐車する際、自動車を道路の端に寄せること。②走行中に横にずらして、隣を走る車に接近すること。 |
| ハードトップ | 自動車のボディスタイルのひとつ。 |
| バードビュー |
鳥瞰図。 上空から斜めに見下ろしたような形式のもの。 |
| バス | 大量の旅客輸送を目的とする自動車。 |
| ハブ | 車輪(あるいは円盤状の部品)の中心部にあって、車輪の外周にあるリムから出た全てのスポークが一点に集中する部分。 |
| パワステ | パワー・ステアリングの略。 |
| パワー・ステアリング | 自動車において、運転者の操舵(ハンドル操作)を補助する機構である。ハンドル操作が軽くなる。 |
| バン |
貨物車。 同じ形状にステーションワゴンがあるが、バンは商用車(荷物の運搬を主として設計)、ステーションワゴンは乗用車(人間の移動を主として設計)という考え方が主流である。 |
| パンク | タイヤに穴があき、走行できなくなることである。 |
| 半クラッチ |
半クラッチとは、自動車・オートバイのクラッチを完全につないでいない状態のこと。 車両の状態に応じて適切なアクセル操作と半クラッチ操作を行わないと、乗員に衝撃を感じさせたり、クラッチジャダーやエンストを起こしてしまう。こうした操作を多用しすぎると、クラッチ板のダンパースプリングの破損やフライホイール固定ボルトの破断といった重大な事態を招く事にもなる為、MT車の運転者は必ず習得しなければならない技術のひとつである。 |
| 半クラ | 半クラとは、半クラッチの略。自動車・オートバイのクラッチを完全につないでいない状態のことである。 |
| ハンドブレーキ | ハンドブレーキ とは、手を使って操作するブレーキのこと。パーキングブレーキ・サイドブレーキの別称で、駐車ブレーキとも表記される |
| ハンドルの遊び |
動かしても反応しない部分。 これがないと少し動かしただけでタイヤが曲がるのでハンドル操作が非常にシビアとなる。 |
| ハンドルの復元力 |
ハンドルの復元力とは、ハンドルを切った後、力を緩めるとハンドルが元に戻ろうとする力のこと。 通常の運転で、カーブから直線に移るときの運転を容易にするために、適度な復元性は欠かせない。 |
| 反応時間 | 運転者が危険な状態を認知してからブレーキをかけて、実際に聞き始めるまでの時間のこと。 |
ひで始まる用語
| 非公認校 |
非公認校とは、公安委員会の許可を取っていない教習所のこと。 公認校と違って単位の規制がないので、個人の苦手な項目だけを指導するなど、教習に柔軟性がある。 安く料金を設定できるが、指導力は水準に規定がないため、ばらつきがあるとされている。 非公認校の中でも、公安委員会に営業の届け出をしているものを「届出自動車教習所」という。 |
|---|---|
| 非常点滅表示灯 | ハザードランプ |
| 標識 | 道路標識 |
| ピラー |
車体において、窓を囲み屋根を支える柱(英語で「pillar」)の部分。1930年以降は、屋根を支えるだけ無く、車体の強度を左右する重要な車体の構造材となった。 ピラーを太くすると、車体が頑丈になるが視界の確保がしにくい。逆に、ピラーを細くすると視界の確保がしやすくなるが、車体の頑丈さが損なわれる。 |
ふで始まる用語
| 普通自動車 | 日本の自動車区分の一つ。道路交通法で、大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車を指す。車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満、乗車定員が10人以下の条件を満たす四輪車の自動車これにあたる。 |
|---|---|
| 普通自動二輪車 | 日本の道路交通法における車両区分の一つ。排気量が50ccを超え、400cc以下の二輪の自動車(オートバイ)を指す。 |
| フックターン |
二段階右折のこと。右折の手順としては、バイクの二段階右折と同じ。 まず、左車線にいながら右にウインカーを出し、交差点に進入し、さらに左に寄って停車し、待機する。右折する側の信号が青になったら右折をする。つまり、交差点の輪郭に沿って曲がること。 |
| フットレスト | 運転する際に、左足を休めるために設置された固定したペダル状のもの。 日本語では足置き、足かけなどでも呼ばれる。 |
| 不凍液 | 自動車のエンジン冷却水の凍結を防ぐために用いる液体のことである。主な成分はエチレングリコールなどである。 |
| 踏切 |
踏切とは、鉄道と道路が平面交差する場所のこと。 法律上は踏切道という場合もある(踏切道改良促進法など)。 国内の現行法令では、踏切道は踏切保安設備(踏切警報機・遮断機・踏切警報機)を設けたものでなければならないとされている。 |
| ブレーキ |
ブレーキとは、運動・移動する物体の減速、あるいは停止を行う装置のこと。 これらの動作を制動と呼ぶため、制動装置ともいわれる。 |
| ブレーキ・ブースター | ブレーキ・ブースターとは、倍力装置とも呼ばれる自動車のブレーキを構成する部品の一つで、運転手のブレーキ操作力を低減する為の補助を行うシステムである。 |
| フレーム | 自動車の構造の技術。 |
| フロアシフト |
シフトレバーが取り付けられた部位に応じてフロア配置のフロアシフト、インパネ配置のインパネシフト、ステアリングコラム配置のコラムシフトの3種に大別される。シフトレバーとは、エンジンを動力とする自動車のMT車の歯車の組み合わせを選択するレバーのことである。これらの自動車を運転する際、適切な出力や速度を得るためには、運転手が状況に応じて任意にMT車の歯車の組み合わせを変える必要があり、その操作に用いられるのがシフトレバーである。 フロアシフトはこの中で現在最も一般的なタイプで、軽自動車から高級セダンまで幅広く使われている。ほとんどの車種で車体中心線近くに配置されるが、レーシングカーでは競技規定に合わせ、右ハンドルの場合でも右シフトとなっているものがある。 |
へで始まる用語
| ペーパードライバー |
有効な普通車の運転免許証を持っているが、実際に運転しない人のこと。 ペーパードライバーは運転する機会がないので、運転技能や危険予測能力が低下している場合も多い。そのため、久々に運転する際は自動車教習所で実施している「ペーパードライバー教習」(有料)に前もって参加するなどして勘を取り戻しておくことが望ましい。 また、ペーパードライバーに似た概念に「サンデードライバー」がある。これは、休日などたまに機会があるときしか運転しない(ために運転技能が未熟な)ドライバーのことをさす。 |
|---|---|
| ペーパーライダー | 有効な二輪車の運転免許証を持っているが、実際に運転しない人のこと。< /td> |
| ヘッドライト | 前照灯 |
| ヘッドランプ | 前照灯 |
| ベルリーナ |
セダンのイタリア名。 日本やアメリカでは一般にはセダンが一般名称で、イギリス名のサルーンは高級なセダンの事を指すことが多い。 しかし、実質はアメリカとイギリスの呼称の違いであり、JISや自動車技術会での技術的な基準においては、セダンとサルーンの間に変わりがない。 |
ほで始まる用語
| ホイール |
車輪。 元々はタイヤやチューブまで回転部分全てを指している言葉だが、自動車においてはこれら軟質な部分を含まない部分を指す。 |
|---|---|
| ホイールスピン | タイヤの摩擦力が自動車の駆動力を超えて接地力を失いスピンすること。 |
| 方向指示器 |
方向指示器とは、右左折や進路変更の際に、その方向を周囲に示すための保安装置のこと。 方向を灯火の点滅で示すことから、日本ではウインカーと通称される。部品名や整備書にはターンシグナルランプという呼称が用いられてきたが、今日ではユーザー向けのカタログや取扱説明書もターンランプなどの表記へ移行している。 |
| 放置車両確認標識 | 違法駐車している車に対して取り付けられるもの。この場合、車の使用者は反則金を納付しなかった場合、放置違反金の納付が命じられる。 |
| 歩行者横断禁止 | 道路標識のひとつ。歩行者は横断してはいけないことを表す。 |
| 歩行者専用 | 道路標識のひとつ。この標識があると、それより先に歩行者以外は通行することができない。ただし、許可を得た場合は除く。 |
| 歩行者通行止め | 道路標識のひとつ。この標識があると歩行者は通行することができない。車の通行は可能。 |
| 補助ハンドル | 教習所の補助席等に取り付けられているハンドルのこと。教習中に主に危険などを回避するために教官が車を操作できるよう取り付けられている。 |
| 補助標識 | 補助標識とは本標識と一緒に取り付けられる。本標識の意味を補足するためのものである。 |
| 補助ブレーキ | 教習所の補助席等に取り付けられているブレーキのこと。教習中に主に危険などを回避するために教官が車を操作できるよう取り付けられている。 |
| ボディー |
車の全体。 ボディーのデザインで車の印象も大きく変わる。 大きくわけて、1ボックス、2ボックス、3ボックスの3つの形状がある。 |
| 歩道 | 車道等に併設され、歩行者の通行のために構造的に区画された道路の部分をいう。 |
| ホーン | 警笛 |
| 本線 |
本線とは、本線車道のことである。 高速道路で通常走行する車線(本線車線)により構成する車道部分のこと。 |
| 本線車道 |
本線車道とは、高速道路で通常走行する車線(本線車線)により構成する車道部分のこと。 緊急自動車を除く自動車が、他の道路から本線車道に入ろうとする場合には、優先本線車道を通行する自動車の進行妨害をしてはならないという決まりがある。 また、加速車線がある場合にはそこで十分に加速してから本線車道に入り、また、減速車線がある場合にはそこに入って十分に減速しなければならない。本線車道から出る場合には、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。急な車線変更は重大な結果を招きかねない。 |
| 本標識 |
本標識とは、道路標識の分類の1つである。 道路標識の種類は大きく本標識と補助標識に分かれ、さらにこの中の本標識は規制標識・指示標識・警戒標識・案内標識の4つに分類される。 |
| ポンピングブレーキ |
ポンピングブレーキとは、自動車運転技術の1つである。 フットブレーキ徐々にを踏み込み、滑り始めたら少し緩めて再び踏み込む動作を繰り返す技術。タイヤのロックを防ぐことで、急ブレーキ時の制動距離を最小限にすることができる。 しかし、近年ではこの操作を自動で行うABSを搭載した車が普及、人間では不可能なミリ秒単位の反射速度の操作を実現している。 /td> |
| 本免 |
本免とは、本免試験の略称である。 教習所を卒業後、住所を管轄する運転免許センターで受ける試験。これに合格することで、やっと運転免許証の交付される。 |
「ま~も」で始まる用語
まで始まる用語
| 巻き込み |
車が右左折する時に生じる内輪差のこと。特に大型車は内輪差が大きく生じる。 運転席からは死角となるエリアが存在し歩行者やバイクなどを巻き込む可能性が存在するため、右左折する際には巻き込み確認が必要である。 |
|---|---|
| 摩擦抵抗 | 走行中の車には重量や速度により運動エネルギーが生じる。そのため、慣性力や遠心力、摩擦力などの力が働く。運動しているものを止めるために、ブレーキの摩擦抵抗を利用し、コントロールしなければならない。 |
| マニュアルトランスミッション |
マニュアルトランスミッションとは、自動車・オートバイ・鉄道車両などに採用されており、運転者の任意により減速比(ギア)を選択するトランスミッション(変速機)である。一般的には5ないし6段階の前進用ギアおよび1段階の後進用ギアで構成されている。 1990年代以降、一般的な乗用車はAT車への移行が進み、MT車はスポーツモデルや一部の廉価グレードを中心に残るに留まっている。車にこだわりのある方や今後上位車種取得を目指す方にはMT車取得をおすすめだが、乗用車のみを運転する場合には取得までの費用・期間を含めAT車をおすすめする。 |
| マフラー |
マフラーとは、排気システムのことである。 エンジンから排出されるガスをスムーズに排出し、大きな排気音を消音するための装置である。エンジンから排出されるガスは、高音・高圧のためそのまま大気中に放出すると急激に膨張してしまい大きな排気音を出してしまう。 |
みで始まる用語
| 右側通行 | こう配の急な道路の曲がり角で左側道路だけでは通行が困難なところなどに設けられる。 |
|---|---|
| みきわめ |
みきわめとは、技能教習の第1段階の最終項目「教習効果の確認(みきわめ)」のこと。 検定や試験というイメージを持つ人が多いが、検定前の練習+検定に合格できるかのチェックを行うことをみきわめという。これまで受けてきた教習で学んだことをそのまま実践すれば、不安を抱くことはほとんどない。 |
| みきり発進 | 前方の信号が赤なのに青になるだろうとみなして発進すること。道路交通法で禁止されている。信号は必ず前方の信号に従わないと、最悪、事故を引き起こす場合もありうる。 |
| ミニバン |
ミニバンという言葉に規格や技術的な定義は存在しないが、全長に対する室内長と室内高は比較的大きい車種を示す。 一般的には、スペースをセダンよりも広くとり、座席のほとんどは、三列シートになっていて、多人数の人間が座れるものをミニバンと呼んでいる。日本車での3列シートの配置は、1列目がセパレートシート、2・3列目を3人がけのベンチシートとした8人乗り、2列目をキャプテンシート(セパレート)+3列目を3人がけベンチシートとした7人乗り、2列目を3人がけベンチシート+3列目を2人がけのベンチシートとした7人乗りのいずれかが多い。 |
| ミニカー | 道路交通法令において総排出量20cc以上50cc以下または定格出力0.25kW以上0.6kW以下の原動機を有する普通自動車をいう。 |
むで始まる用語
| 無段階変速装置(CTV) | 特性上、エンジン低回転時の動力伝達能力が弱く、低速走行時にアクセルやブレーキのコントロールが難しく、エンジンブレーキがききにくい。 |
|---|---|
| 無免許 |
無免許とは、無免許運転の略である。 運転するのに免許が必要な機器を、免許を得ないままに運転することである。 |
| 無免許運転 |
無免許運転とは、免許を取得していないのに運転を行うことである、以下の条件下が無免許運転にあたる。 ①免許証を取得していないのに運転したとき。②試験に合格後、交付前に運転したとき。③免許証有効期限が過ぎた後、運転したとき。④免許の取り消し処分を受けたのに運転したとき。⑤免許の停止、仮停止中に運転した時。⑥その免許では当てはまらない(運転できない)車種の車を運転したとき。 |
めで始まる用語
| 免許 | 広く用いられる用語ではあるが、一般的に免許とは禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許す行政処分のこと。特定の人に権利を定めて地位を与えることである。 |
|---|---|
| 免許合宿 | 免許合宿とは短期間の合宿で免許を取得することである。合宿免許ともいう。メリットは、短期間で且つ通学よりも低価格で免許を取得できる点である。 |
| 免停 | 免停とは免許停止のことである。運転免許を取得した者が、道路交通法の違反による点数が加算され、過去3年間の累積点数が一定の点数に達した場合に、30日~180日の期間を定めて、違反者の免許の効力を停止させることです。 |
| 免取 |
免取とは、免許取消の略である。 違反や事故によって加算される一定の点数が積み重なり、免許取消となる。免許取消になると、運転免許試験場で試験を受け直さなければ、再び運転することができなくなる。免許取消後、すぐには再取得ができず、欠格期間がある。 |
もで始まる用語
| 目視 | 運転中バックミラーに写らない部分が存在するので、直接目を向けて目視して確かめることである。 |
|---|---|
| モータースクール | モータースクールとは、自動車学校の別称である。教習所によって使い分けられている。 |
| モノコックボディー |
モノコックボディーとは、フレームとボディを一体に作った車体のことである。 1980年代以降、自動車のほとんどに用いられているボディ構造。フレームレス構造とも呼ばれる。 |
「や~よ」で始まる用語
やで始まる用語
| 焼き付き | 焼き付きとは、エンジンをはじめとする金属同士の摩擦部分において、冷却不良や潤滑不良などが原因で過熱し、融けて固着してしまうこと。油圧の低下やエンジンオイルの品質・管理不良などが原因となる。 |
|---|
ゆで始まる用語
| 優先(広路・左方・路面電車) | 交差する道路が優先道路であるとき、交差する道路の道幅が広いときは徐行するとともに交差点の道路を通行している車や路面電車の進行を妨げてはいけない。また道幅が同じような道路の交差点では左方から進行してくる車が優先である。そのほかに、交差点では右方左方関係なく路面電車の進行を妨げてはならない。 |
|---|---|
| 優先通行帯 | 優先通行帯とは、路線バス等の優先通行帯を示しており、路線バス等が接近してきた場合には、小型特殊自動車や原動機付自転車、軽車両以外の車は他の通行帯に出なければならない。また、混雑時など優先通行帯から出られなくなる可能性が想定される時には通行してはいけない。 |
| 優先道路 | 優先道路とは、交差点など道路標識または道路標示によって指定された道路で、交通整理が行われていない交差点の進入時に徐行する義務がないもの。 |
| 優良運転者 |
優良運転者とは、継続して免許を受けている期間が5年以上で、かつ5年以上無事故無違反及び無処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷がない者のことである。 「優良運転者」で「優良運転者講習」対象者には、ゴールド免許が交付される。 |
よで始まる用語
| 幼児等 |
幼児等とは幼児及び児童の事で、幼児とは6歳未満の者、児童とは6歳以上12歳未満の者を指す。 道路交通法14条で、保護者は交通頻繁な道路、踏切とその付近で遊ばせたり一人歩きをさせてはならないと規定している。 |
|---|---|
| 予熱栓 | 予熱栓とは、冷間時の始動を助ける補助熱源である。グロープラグとも呼ばれる。 |
| 4WS |
4WSとは、四輪操舵(よんりんそうだ)のことである。4 Wheel
Steering(フォー・ホイール・ステアリング・システム)の略。 通常は前輪だけで操舵するが、このシステムは後輪も同時に向きを変え、タイトコーナーでの小回りや高速旋回時の走行安定性を高める。 |
| 4WD |
4WDとは、四輪駆動(よんりんくどう)のことである。略称は四駆(よんく)。 4つある車輪すべてに駆動力を伝え、4輪すべてを駆動輪として用いる方法のこと。 一般的な二輪駆動と比べると、四輪が駆動力を発揮するため、牽引力は大きく向上するのが特徴である。 |
「ら~ん」で始まる用語
らで始まる用語
| ライダー |
ライダーとは、「乗り物に乗る者(騎乗する者)」を示す英単語である。 元々「馬に乗る」「馬にまたがる」のように使われていた単語なので、車のようなものよりバイク・オートバイのような「またがる」人のことをライダーと呼んでいる。 |
|---|---|
| ラウンドアバウト | 信号機のない、ドーナツ型の交差点のこと。 |
| ラジアルタイヤ | カーカスがタイヤの中心から放射線状に配置されている構造にタイヤのこと。メリットは、操縦性などに優れ、発熱が少ないことなどが挙げられる。 |
| ラジエター | ラジエターとは、エンジンを冷やすための冷却器でエンジンの前にあり、走行中風を受ける事で中の水が冷える仕組みになってる。ラジエータ・ラジエーターなどと呼ばれることもある。 |
| ラップ | ラップとは、1周・1往復のことである。 |
| ラップタイム | ラップタイムとは、1周(1往復)するのに要する時間のことである。 |
| ランオン |
ディーゼリング。 エンジンのスイッチをオフにして点火を止めてもエンジンが回転し続けること。 |
| ランドマーク |
ランドマークとは、元来の文字上の意味としては、探検家などの人が一定の地域を移動中にまたそこに戻ってくるための目印とする地理学上の特徴物を指す。 カーナビゲーション用の地図、携帯電話による道案内用の地図などの電子地図において、著名な建物などを特に「ランドマーク」として扱い、地図画面上に実物を模したアイコンを表示したり、その建物に関する詳細情報を案内することがある。ランドマークはその都市の顔となり、住民に親しまれるとともに、来訪者に強い印象を与える。 |
りで始まる用語
| リバースステア |
リバースステアとは、自動車が旋回するとき、ハンドルの切れ角が一定であるにもかかわらず、速度が遅いときは車の回転半径がだんだん大きくなり、速度を速くすると回転半径がだんだん小さくなる現象のことである。 タイヤのコーナリング特性やロールステア、コンプライアンスステア、アライメント変化、サスペンションばね定数などの非線形性により、前後のグリップバランスが変わることによって起こる。リバースには逆転の意味がある。 |
|---|---|
| リム |
リムとは、車輪の外縁部にあって全体の形状を支えている硬質の円環のことである。 自転車やオートバイの場合、内側はスポークでハブに固定され、外側はタイヤを挟んではずれないよう押さえている。 自動車や一部のロードバイクの車輪には、リムとスポークが融合した形状の物もある。 |
| リムジン |
(1)職業運転手が運転する事を前提とした、大型の高級車のこと。 (2)後部座席部分の構造を延長し、運転席との間に仕切りを設けた大型乗用車のこと。 (3)特定区間を連絡するシャトルの一種であるバスや大型のバンのこと。 元々は馬車の形式の一つであり、御者と客室の間に仕切りがある、もしくは御者席が客室の外側にあるもののことである。なお、この様な仕切り(パーティション)を設けたリムジンが、現在においても最も格の高い正式なリムジンとされている。 |
| リムジンバス |
リムジンバスとは、内装が豪華なバスを指し、観光バスなどに供されるバス車両のことである。 空港などと周辺市町村を連絡するバス車両と運行形態であり、空港リムジンバス、エアポートリムジンバス、空港連絡バスとも呼ばれる。 |
| リーンバーンエンジン |
リーンバーンエンジンとは、燃費を良くするために、通常よりも少ないガソリンの量で燃焼させるシステムをもったエンジンンのことである。 具体的には、重量比で空気16に対してガソリン1が理想とされてきたが、これより薄い混合気を用いるエンジンのことである。 |
るで始まる用語
| 累積点数 | 累積点数とは、交通違反に付けるもの(基礎点数)と、交通事故に付けるもの(事故点数)、ひき逃げなどに付けるものの、それぞれを合計点のことである。免許の点数は、減点方式ではなく加点方式で、累積点数が一定の基準点数が超えた場合に行政処分となる。 |
|---|---|
| ルーフキャリア | 自動車の屋根につける荷台のこと。 |
れで始まる用語
| レッドゾーン |
レッドゾーンとは、エンジンの回転数が限界に近い領域のこと。 タコメーターで赤く記されていることから、このように呼ばれる。 |
|---|---|
| 冷却水 |
冷却水とは、高熱を発する機械などを冷やすために用いる水のことである。 エンジン内部を循環する冷却水は、冬場の暖房の熱源としても使われている。 |
| レブリミッター | エンジンの回転数を監視し、設定の最高回転数を超えないように抑制する仕組みの装置。 |
ろで始まる用語
| 路肩 | 道路を保護するためまたは車道の効用を保つために、車道や歩道などに接続して設けられている道路の橋の帯状の部分のことをいう。 |
|---|---|
| 路線バス | 路線バスとは、国土交通省より道路運送法に規定される「一般乗合旅客自動車運送事業」の許可を受けた路線を運行し不特定旅客を運送するバスである。乗合バス(のりあいばす)とも呼ばれる。都市間高速バスや「はとバス」に代表される定期観光バスもこの業態で運営されている。 |
| 路線バス等優先通行帯 |
路線バス等優先通行帯とは、路線バスが道路の定められた部分を通行するようにするために、白線などの道路標示によって示されている部分のことである。 路線バスなどが接近してきた場合には、小型特殊自動車や原動機付自転車、小型特殊自動車以外の車は他の通行帯に移らなければならない。また、混雑時など優先通行帯から出られなくなることが想定される時には通行できない。 |
| 路側帯 |
路側帯とは、歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。 歩行者の安全のために、歩道がない道路又は道路の歩道がない側に設置され、車道と分離することにより基本的に歩道と同様に扱われる。 |
| ロータリーあり | 道路標識の警戒標識「ロータリーあり」を指す。前方にロータリーがあることを示している。 |
| ロービーム |
ロービームとは、前照灯のことである。操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させるために使われる照明装置。 ヘッドランプやヘッドライトと呼ばれることもある。大抵は機械の前面に透明(色が付いていても青や黄などで、薄い色)のレンズを持つランプ(灯体)が付けられている。 |
わで始まる用語
| ワイパー |
ワイパーとは、ガラス外側表面に付着した雨滴・雪、汚れなどを払拭して視界を確保する装置である。 主要な構造はゴム装着のワイパーブレードを取り付けたワイパーアームを左右に振って水滴などを払拭して操作者の視界を確保するものであり、基本的な構造は発明されて以来100年以上ほとんど変わっていない。 |
|---|---|
| ワイパーブレード |
ワイパーブレードとは、ワイパーのゴム以外の部分のことである。 ワイパーブレードの寿命は約1年であり、定期的な交換が必要である。 |
| 若葉マーク |
若葉マークとは、初心運転者標識の通称である。 矢羽のような形状をしていて、左が黄色、右が緑に塗り分けられ、若葉のように見える事からこのように呼ばれる。また、他にも初心者マークと呼ばれることもある。 |
| ワゴン |
ワゴンとは、自動車の形態のひとつである。ステーションワゴン・トールワゴン・ミニバン・ライト版・ワンボックスカーに対して使用されることがある。 またバンと似た形状だが、バンは商用車(荷物の運搬を主として設計)、ワゴンは乗用車(人間の移動を主として設計)という考え方が主流である。 |
| わだち | 車が通った車輪の跡の事をいう。 |
| 割り込み |
割り込みとは、車両の運転においては他の車両の進路上の前方に進路変更する行為を指す。 赤信号や、徐行、一時停止などするべき場所や、混雑・渋滞などにより、徐行・停止している車両や車両の列に追いついた場合は、その車両列等を避けるために、その車両列等の横を通過して、その車両列等の進路上の前方に進路変更し、またはその車両列等の進路上を横断してはならない、と言うことである。 |