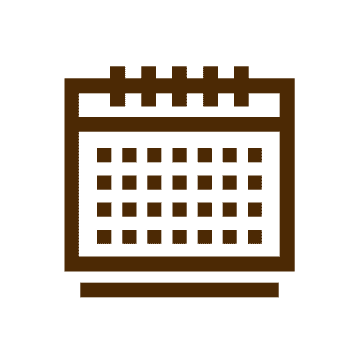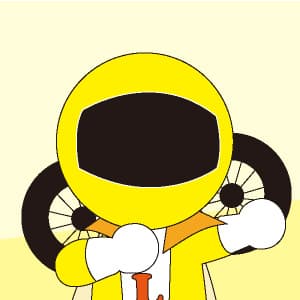
遠い所で暮らしながら教習するんだよね。何を持ってけばいいか混乱しちゃうよ…。

そうだな。じゃあ、必要なもの・服装の注意点・あると便利なものに分けて、一つずつ解説するぞ!
合宿免許で必要な持ち物リスト
入校時・手続き時に必要な持ち物
- 本籍地記載の住民票
- 本人確認書類(所持免許がある人は運転免許証)
- 諸経費
- 印鑑(認め印)
- 黒ボールペン(書類用)
外国籍の方が必要な持ち物
- 在留カード(旧:外国人登録証明書)
- 国籍記載の住民票
- 本人確認書類(所持免許がある人は運転免許証)
- 諸経費
- 印鑑(認め印)
- 黒ボールペン(書類用)
上記持参品の注意点
- 住民票について
- 下記の条件を満たす原本(コピー不可)を用意してください。
-
- 入校3ヶ月以内に交付されたもの
- マイナンバーの記載がないもの
- 本人確認書類について
- 下記のうちいずれか原本(コピー不可)を用意してください。
-
- 健康保険の被保険者証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- ※住民基本台帳カードは、2015年12月限りで新規発行は終了しました。
- ※所持免許がある人は下記「運転免許証」をお持ちください。
- ※上記の身分証明書の準備が難しい方は必ず事前にご相談ください。
- お持ちの運転免許証についての注意点
- 入校期間中に有効期間が切れる可能性がある場合は必ず更新手続きを行い、有効期間に余裕があるものを用意してください。
- 免許証記載の住所が住民票記載住所と異なる場合は、入校前に住民票住所に統一する必要があります。
- 紛失した方・失効してから6か月以内の人は再交付したものを用意してください。
- ※破損・汚損した免許証を受け付けない教習所もあります。各教習所の注意事項(料金と保証内容)と自身の免許証を確認し、該当する場合は再発行した新しいものを用意してください。
- 諸経費について
- 教習中に仮免許を取得する場合、仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)を現地で支払うことになります。
- 他にも、教習所によっては教本代・写真代・原付教習代等が現地払いになります。
- 印鑑(認印)について
- 教習所の中には、インク補充型(シャチハタ等)・ゴム印が不可なところもあります。お申し込みの際にご確認ください。
- 黒ボールペンについて(書類用)
- 消せるタイプのボールペンは、書類に使用できません。
- 在留カードについて(旧:外国人登録証明書)
- 入校期間中に有効期間が切れる可能性がある場合は必ず更新手続きを行い、有効期間に余裕があるものを用意してください。
- 下記の項目が記載されているものを用意してください。
-
- 国籍、地域
- 在留期間満了日
- 在留カード番号
- 在留資格
教習に必須な持ち物
- 筆記用具(鉛筆・消しゴム等)
- メガネ・コンタクトレンズ(必要な方)
生活で推奨する持ち物
- 着替え
- 普通免許で約2週間、普通二輪免許で1週間超滞在するため、着替えが必要になります。
- といっても、2週間分を持っていくと荷物がかさばりますので、3日分くらい持っていって洗濯して着まわすことになります。
- また、一部のホテルを除く宿泊施設はナイトウェアを用意していません。夜に着るためのパジャマやジャージも用意しておくのがオススメです。
- スマートフォン&充電器
- 「充電器もセットで」忘れずに持っていきましょう。スマートフォンだけ持っていって「しまった…」と現地調達した合宿生も少なくありません。
- 雨具
- 一部の教習所では、校舎と宿泊施設の間や教習車・送迎バス乗り場などにおいて、雨が防げないことがあります。特に梅雨や秋雨の時期には、傘(折り畳み傘がオススメ)を持っていく必要があります。
- また、バイク教習は雨天決行になる場合も少なくありません。特にバイク教習を受ける人は、動きやすい雨合羽を持っていきましょう。
- 現金・キャッシュカード
- 合宿期間中は、手続き以外にもお金が必要になる局面があります。詳しいことは下のコラム「現金はどれだけ持っていけばいいの?」をご覧ください。
- ハンガー・洗濯用品(一部宿泊施設は除く)
- 一部の宿泊施設には、ハンガー(上着用・洗濯用)や洗剤を設備していません。また、洗濯バッグや洗濯バサミ、洗濯ネットに至っては、多くの宿泊施設において用意がありません。
- ただ、周辺施設や品物によっては、現地調達・使い捨てができます。
- まずは宿泊施設の「部屋設備」表や「周辺施設」表を確認したうえで、自身の洗濯習慣とも照らし合わせて、何を持っていくか計画しましょう。
- タオル類(一部宿泊施設は除く)
- ホテルを除く宿泊施設のほとんどは、タオル類を設備していません。
- 宿泊施設の「部屋設備」表や「周辺施設」表(周辺施設によっては現地調達も可)をご確認ください。
- 歯ブラシ・洗面セット・カミソリ(一部宿泊施設は除く)
- 一部の宿泊施設には、歯ブラシやせっけん、シャンプー、リンス、カミソリを設備していません。設備があっても、相部屋プランのある施設では共同利用になることも少なくありません。
- 宿泊施設の「部屋設備」表や設備状況、「周辺施設」表(周辺施設によっては現地調達・使い捨ても可)をご確認ください。
- 常備薬(必要な方)
- 持病がある方、体調に不安がある人は必ず持っていきましょう。
- 薬の種類などにもよりますが、ピルケースや携帯ポーチなどに入れて整理するのがオススメです。
- ただし、運転において適さない常備薬もございます。薬の服用をして運転をしてよいかどうかはかかりつけの医師、また薬局で購入した場合は説明書を必ず確認しましょう。
- スタイリングセット・化粧品(使用する方)
- 折り畳めるクシ、小さなパレットなど、コンパクトで持ち歩きやすい物がオススメです。
- 延長コード付き電源タップ
- 宿泊施設によっては、コンセントの数が少なかったり、設置場所が不便だったりする場合があります。
- 特に相部屋プランでは、一部屋のコンセントの穴を複数名で共有する事になります。
- そのような場合になると、延長コード付き電源タップがあれば重宝します。
- 綿棒
- 基本的に宿泊先に準備はありません。気になった時に耳をかけるので、あると快適です。
- 爪切り
- 爪は1週間で1mm近く伸びるので持っていくのがオススメです。
- スリッパ
- 宿泊施設によって、設置がない所(特にマンションタイプ)があります。また、設置がある施設でも、ホテルを除けば共同利用になる場合があります。
- 衛生面が気になる人は、ぜひ用意してください。
- ※一部宿泊先では持参必須もあります
- ドライヤー
- 設置がない宿泊施設は少なくありません(特に学校寮)。また、設置があっても風力などが自身にとって十分でないことがあります。
- 衛生面が気になる方・ドライヤーにこだわりがある人は持っていきましょう。これらの点にこだわりがない人は、宿泊施設の「部屋設備」表や設備状況を確認したうえで、持っていくべきか決めるのがオススメです。
- 衣類圧縮袋
- 合宿免許では三日分の服を持っていくことになりますが、そのまま持っていくとかさばることがあります。
- 衣類を圧縮袋に入れて整頓すれば、荷物がかさばる事を防げます。
- ばんそうこう
- 靴擦れや自炊中の切り傷など、合宿期間中にちょっとしたけがをすることもあります。そんな時のために用意しておくと安心です。
- 安眠グッズ
- よく眠れることは、体力勝負の教習生活を乗り切る重要なカギになります。
- 必要な方(特に相部屋プランの方)は耳栓・アイマスクなどの安眠グッズを用意しましょう。
- また、いびきをかくと指摘されている人は、相部屋プランで泊まる場合、いびき防止グッズも用意しておきましょう。
- インターネット回線関係機器(ポケットWiFiなど)
- 多くの教習所ではWiFiが完備されていますが、多くの方が利用します。
- ブラウザを見るには問題ないかと思いますが、アプリ利用などで重く感じることもあるかもしれません。
- また、一部宿泊先ではWiFiがありません。
- 普段使いのバッグ
- 合宿期間中は、教習用品(学科教本・ノート・文具など)を宿泊施設や校舎で持ち歩くことになります。
- その際に便利になるのがマイバッグです。サイズは、A4・厚さ6mm程度の本が3冊入る程度のものであれば十分です。
- 教習所によっては、入校特典として支給される場合もあります。
合宿免許に適した服装
合宿で車やバイクを運転する際の服装について解説します。
多くの教習所では、運転の基本として下にあるようなルールを設定していますが、一部の教習所では、特別なルールが追加される場合もあります。
詳しいことは、各教習所の注意事項(料金と保証内容)も確認をお願いします。
四輪車(普通車など)教習の場合
- 運転しやすい服装
- 着物やスカート、裾が極端に広いズボンは、運転操作の妨げになりますので教習できません。
- とはいえ、タイトすぎる服では、座学で疲れやすくなるだけでなく運転操作も難しくなります。ゆったりとしたデニムやひざ下丈のワイドパンツを着用するのがオススメです。
- また、露出の多い服(タンクトップ、ホットパンツ等)も、安全面(シートベルトとの摩擦)・衛生面から禁止されています。
- 運転しやすい靴
- スニーカーなど、足の力が伝わりやすい靴を用意しましょう。
- サンダル、下駄、ハイヒールや厚底ブーツなどで運転してはいけません。
- 爪
- ハンドルを握りやすいように、付け爪を外したり長すぎる爪を切ったりしなければならないことがあります。
- 長袖・長ズボン・手袋(原付教習のみ)
- 転んだ時のけがを最低限に抑えるように、肌の露出をなくしましょう。暑い夏でも、通気性が良い服を着るなどしてこの服装を厳守しましょう。
- また、動きやすいものを着ていきましょう。
バイク教習の場合
- 長袖・長ズボン
- 転んだ時のけがを最低限に抑えるように、肌の露出をなくしましょう。また、動きやすいもの・なるべく目立つ色のものを着ていきましょう。
- 暑い夏でも、この服装を厳守しましょう。ただ、一部の夏用ライダーウェアは通気性が良いものもあります。特に免許取得後もバイクに積極的に乗ろうと考える方は、専用ウェアの用意をオススメします。
- 靴下
- 足首より上まであるものを用意しましょう。スニーカーソックスでは教習できません。
- グローブ
- 手指を動かしやすいもの・できるだけ摩擦に強いもの(革製など)を用意しましょう。
- 一部の教習所では、滑り止め付きの軍手でも可能です。
- ヘルメット
- 下の条件を満たすものを用意してください。(教習所により規定が異なる場合がありますので必ず確認しましょう)
-
- フルフェイス or ジェット型のもの
- PSCマーク or CGマーク or JISマークがあるもの
- 頭のサイズに合うもの(左右に動かすと頭に引っかかる)
- あご紐がかけられるもの(紐と首の間に指一本入る程度が目安)
- 一度も大きな衝撃を受けていないもの(受けたものは耐久性が下がるため)
- 一部の教習所では貸し出しがありますが、衛生面が気になる方は自身のものを用意するのがオススメです。
- 靴
- ※教習所により規定が異なる場合がありますので必ず確認しましょう
- ひもがなく、かかとがしっかりした(ペダル・ステップを踏める程度)ものを用意してください。ほとんどの場合、ライダーブーツやハイカットの運動靴で問題はありません。
- もちろん、普通車と同じくサンダル・ハイヒールは不可です。また、教習所や車種によっては運動靴・スニーカーが禁止になる場合があります。
- 可能であれば、手袋と同じくできるだけ摩擦に強いもの(革製など)を用意しましょう。通気性(特に夏場)や伸縮性があるとベターです。
空き時間にあると便利グッズ
- スマートフォン&モバイルバッテリー
- スマートフォン1つあれば無限に時間を潰せる…。そんな方も多いのではないでしょうか。
- ゲームなどの娯楽だけではなく、テスト問題の練習アプリもあります。
- しかし教習所では常に充電できる環境があるとは限りません。
- モバイルバッテリーがあれば安心ですね。
季節ごとの持ち物
- 虫刺され対策グッズ(春・夏・秋にオススメ)
- 校舎や宿泊施設が山あいにある場合は、周辺に虫が出ます。
- 入校時期や教習所の写真を見つつ、必要があれば虫よけスプレー・かゆみ止めを持っていきましょう。
- 替えの靴(雨・雪の季節にオススメ)
- 雨の多いシーズンでは、荷物に余裕があれば替えの靴を持っていくと安心です。長靴を雨の時は履いて、運転する時はスニーカーに履き替えるのもおすすめです。
- また、雪国にある教習所の中には、冬に雪用ブーツの用意を呼び掛けている所もあります。そのような教習所では、運転・室内用の靴と雪用ブーツを用意し、使い分けていきましょう。
- 使い捨てカイロ(冬にオススメ)
- 技能教習で冷えた車内に入る時や校舎・宿泊施設周辺を散策する時に重宝します。
- 乾燥対策グッズ(冬にオススメ)
- 冬の屋内は暖房機器が動きますので、乾燥しやすくなります。特に関東・東海・関西・瀬戸内海側の地方は、その気候のため屋外でも乾燥します。
- 乾燥が厳しいと、手指やのどにダメージを受けやすくなります。ハンドクリームやのどスプレーを持ち歩いたり、部屋に小さな卓上加湿器(一部のホテルには設置あり)を置いたりして対策しましょう。
それぞれのシーズンでオススメな服装に関する詳しい情報は、下のページにも詳しく載っています。合わせて確認しましょう。
持ち物に関するお役立ち情報
持っていくものを減らすには
ここまでいろいろな持ち物を紹介しましたが、かなり多いと感じる人も多いと思います。
もちろん、入校時・手続き時や教習に必要なもの(服装)は、入校時に手元にあるようにしておかなければなりません。しかし、一部の生活グッズは、場合にもよりますが合宿の行き・帰りの際に持っていかなくてもよいものがあります。
そこで、生活グッズに関して少し工夫をすることで、行き・帰りの際に少しでも荷物を減らせる場合をいくつか紹介します。
- 宿泊施設の設備を利用
- 一部の持ち物の所でも紹介されていますが、グッズや宿泊施設によっては、建物内に設置されているものがあります。
- 多くのホテルではタオル・歯ブラシセット・ナイトウェアなどのアメニティがありますし、一部の学校寮でもシャンプーなどが設置されていることがあります。
- 設備をどこまで利用できるか把握したうえで、持っていくもの・行かないものを決めるのがオススメです。
- まずは、宿泊施設の「部屋設備」表をご確認ください。詳しく知りたい方は「合宿免許ネクスト」までお問い合わせ頂いても大丈夫です。
- 現地購入
- これも一部の持ち物の所でも紹介されていますが、校舎や宿泊施設の周辺にお店があれば、消耗品や一部のグッズは現地購入できます。洗剤や小型のばんそうこう・カイロなどがいい例です。
- また、食事なしプランの方は、外食をしない限り食品をお店で購入することになります。
- まずは、教習所の「教習所の設備と周辺環境」表や宿泊施設の「周辺設備」表を確認してどんなお店があるかを把握し、現地で買えるものをイメージしましょう。
- 宿泊施設まで郵送する
- 一部の教習所では、行き、または帰りで手荷物を宿泊施設まで届けることができます。「現地調達を計画してもまだ荷物が多そう…」という方にはオススメです。
-
その場合、下の4点にご注意ください。
・持ち歩かなければならないものに対しては、利用できない
・郵送費をサービスする教習所・しない教習所がある
・発送条件に制限がある
・郵送できる教習所・宿泊施設は限られている - 特に下3つの条件に関しては、教習所などによって異なります。詳しいことはお問い合わください。
現金はどれだけ持っていけばいいの?
実際の合宿生活には、教習関連の費用を除いても、以下の費用がかかります。
- 交通費(一部の教習所は除く)
- 交通費の支給額は教習所などによって異なりますが、全額支給される場合は多くありません。
- このため、行きや帰りで2,000円~30,000円程度かかる場合もあります。
- 食費(食事なしプランのみ)
- 自炊など食事がないプランが安いのは、教習所で食費を負担しなくてよいからです。その分、食事は自身で調達、食費は自身で負担することになります。
- 1日の食費を約1,500円と見積もると、1,500×合宿日数分かかり、普通車合宿では2万円を超えることもあります。
- ただ、料理も自身でこなすと想定すれば、少しは食費を抑えることもできると考えられます。
- 洗濯代(一部の教習所のみ)
- 一部の教習所・宿泊施設では、有料の洗濯機・乾燥機を利用することになります。
- 洗濯1回100円・乾燥1回200円を3~4回繰り返すと想定すれば、普通車合宿では900円~1200円程度かかることになります。
- 少し余談になりますが、有料の洗濯機・乾燥機を利用する場合は、手持ちの100円玉を切らさないようにしましょう。
- 間食
- 体力を消費しやすい合宿期間中は、お菓子やジュースなどが欲しくなること考えられます。特に、夏場はこまめな水分補給も必要になります。
- 1日に150円~200円消費すると考えると、普通車合宿では2,100円~3,200円程度かかることになります。
- その他
- 校舎や宿泊施設の周辺施設を利用したり生活グッズを現地調達・郵送したりすれば、その分お金がかかります。
- この分のお金は、教習所や自身のライフスタイルによって大きく異なります。さらに、不足な事態も加味すれば、どれだけお金を持っていけばよいか見積もりがつきにくいところです。
- 合宿期間中どんな施設を利用して・何を買って・どれだけお金を使うか、可能な限り事前にイメージしておきましょう。
ここまで挙げれば、教習関連の費用を除いても、合宿先で4万円程度支払うことになると想定されます。ただ、教習所・宿泊施設の状況や自身のライフスタイルによっては、実際にかかる金額はこれよりも安くなったり高くなったりします。
ただ、数万円の現金を持って歩くのはセキュリティ上よくありません。キャッシュカードを携帯したうえで、校舎・宿舎周辺のATM(またはコンビニ・ショッピングモール)の場所を真っ先に把握しておきましょう。
まとめ
ここまでさまざまなグッズやマメ知識を挙げていきましたが、特に重要な点4か条をまとめました。
- 合宿免許の持ち物は、手続きや教習に必要なもの・生活に必要なもの・生活に便利なものに分けられる!
- 生活関連のものは、宿泊移設や周辺店舗で現地調達できるものもある!
- 教習の服装にはルールあり。特にバイクは特別な道具もあるから気をつけよう!
- 教習や合宿生活で現金が必要。キャッシュカードは必携・ATMの位置も把握しよう!

必要なもの・現地調達するものは、リストにまとめると便利だな!
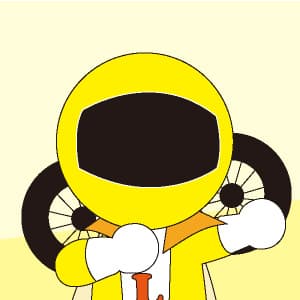
手続き・教習に必要なものは入れた場所も覚えておこう!